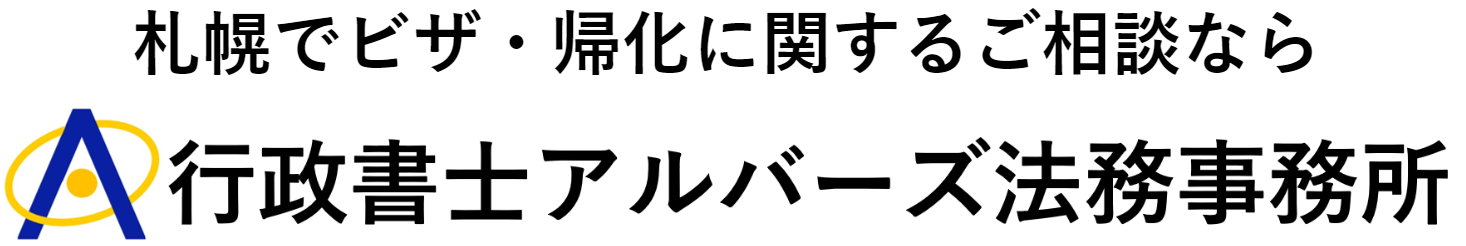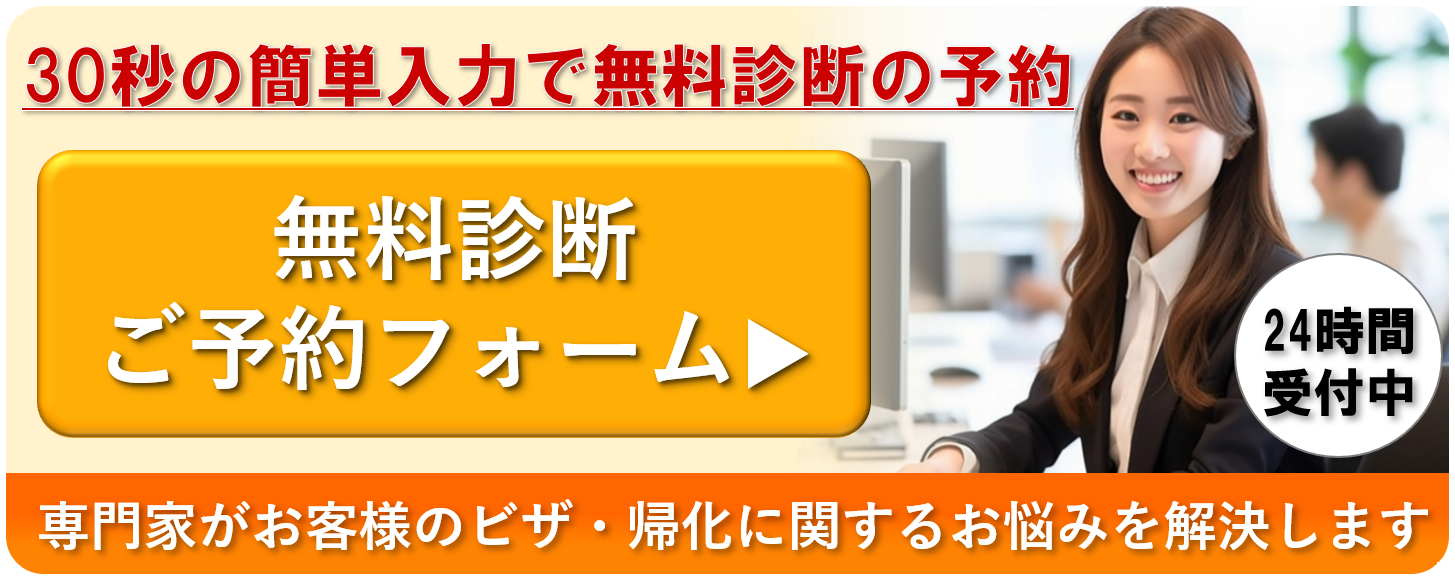日本の永住権を取得する4つのメリットを解説

日本の永住権(在留資格「永住者」)を取得すると、在留期間や就労制限から解放され、日本での生活や将来設計が格段に安定します。
そのため、「永住者」は日本で長く生活を続けたい外国人にとって最終目標のビザとも言えます。
ちなみに、札幌に住む外国人の最も多い在留資格が「永住者」です。
(2025年6月時点 札幌市内の永住者:3,728人)
この記事では、日本の永住権を取得する4つのメリットについて、ビザ専門の行政書士が解説いたします。
これからも日本での生活を希望する方の参考になれば幸いです。
日本の永住権を取得する4つのメリット
日本の永住権を取得することの主なメリットは、次の4つがあります。
① 在留期間が無期限になり、ビザ更新が不要
1つ目のメリットは、在留期間が「無期限」になり、定期的なビザ(=在留資格)の更新手続きが不要になることです。
ビザには、それぞれ在留期間が定められています。(※ 一部を除く)
例えば、配偶者ビザなら在留期間「5年、3年、1年、6か月」のいずれかです。
そのため、引き続き日本に滞在する場合は、ビザの在留期限が来る前に「在留期間更新許可申請」が必要となります。
しかし、永住者なら在留期間が「無期限」となり、ビザの更新手続きが不要です。
ビザの更新は、意外と手間のかかる手続きでありながらも、もし不許可になったり、更新手続きを忘れたりした場合は、日本で生活することができなくなってしまいます。
そのような、万が一の事態を考えると、永住者の在留期間「無期限」は大きなメリットと言えます。
ただし、「在留カード」の更新は、「7年ごと」に必要ですので、忘れないよう注意しましょう。
| 一般的なビザ | 永住者 |
|---|---|
| 定期的なビザ更新が必要 | ビザ更新が不要 ※在留カードは7年ごと |
② 仕事の制限が無く、自由に好きな仕事ができる
2つ目のメリットは、仕事内容の制限が無くなり、自由に好きな仕事ができるようになることです。
就労ビザは、仕事の内容によって取得すべきビザが異なります。
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人は、会社経営の仕事をすることができません。
このように、現在持っている「就労ビザ」に関する仕事しかできないため、仕事内容の変更を伴う転職をする際には、その都度、就労ビザの変更手続きが必要となります。
しかし、日本の永住権(在留資格「永住者」)には仕事の制限がないため、転職も起業も自由に行うことができます。
| 就労ビザ | 永住者 |
|---|---|
| 仕事の制限あり ビザごとに定められた仕事しかできない |
仕事の制限なし |
③ 社会的信用度が高くなる
3つ目のメリットは、社会的な信用度が高くなることです。
日本の永住権は審査基準が非常に厳しく、取得そのものが簡単ではありません。
そのため、
と見なされ、社会的な信用度が高く評価されます。
日本で長く暮らす上で、この「信用力」は大きな意味を持ちます。
例えば、住宅ローンや融資、クレジットカードの審査では、「永住者」であることが「長期的に日本に滞在し、安定して生活していける証拠」としてプラスに作用するからです。
結果として、審査に通りやすくなり、将来の選択肢を大きく広げることができます。
④ 万が一、離婚(死別)しても日本に滞在できる
4つ目のメリットは、もし日本人/永住者の配偶者と離婚・死別してしまったとしても、そのまま日本に滞在できることです。
「永住者」は在留資格(ビザ)の中でも「身分系資格」に分類され、他に「日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」の3つが該当します。
例えば、在留資格「日本人の配偶者等」は”日本人の配偶者という身分”として日本に住むことを許可された外国人が持つビザです。
つまり、在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国人が、もし離婚・死別してしまった場合は”日本人の配偶者という身分”では無くなり、そのままでは日本で生活することができなくなってしまいます。
引き続き日本に滞在する場合は、6か月以内に「就労ビザ」または「定住者」への在留資格変更許可申請が必要となります。
しかし、「永住者」の場合は、もし離婚・死別してしまったとしても、特にビザの手続きは不要で引き続き日本に滞在することが可能です。
最後に 日本の永住権のメリットは大きい
以上、日本の永住権を取得する4つのメリットについて解説しました。
永住許可申請の許可率は約50%であり、「2人に1人は不許可」になっています。
日本の永住権を取得するためのハードルは高く、審査はかなり厳しいです。
しかし、ハードルが高いからこそ、日本の永住権のメリットはとても大きいです。
と検討されている方は、今のうちに永住権取得へ向けた対策を始めることがおすすめです。
ビザ専門家である当事務所が日本の永住権取得に向けて、必要な対策をご提案いたします。
ご相談は無料ですので、まずは初回相談にてお話をお聞かせください。